�ّ�ɋ����郁�C����(�����H)���u�́AWestern Electric �h���C�o�[���j�b�g�v�d�T�X�S�`�^���A�T�X�S�`��p�ɊJ�����ꂽ�I���W�i���̂Q�S�`�z�[���ɑ����������̂��B����ɒቹ�����ǂ̂悤�ɕt�����Ă��������ۑ�ł���B�����G�l���M�[�I�ɂ́A�T�X�SA+�Q�SA�ɏ��Ă�E�[�t�@�[�́A�z�[�����[�h�Ȃ��ł�4181����18�C���`�̗㎥�E�[�t�@�[���S����R���B�z�[�����[�h�������Ă��Q���͕K�v�ƂȂ�B������o�b�t���ɂ���ƁA�����̈�قƂ�����Œ��������Ȃ��B����𓌋��̋����l�̏Z��Ŗ炵�Ă݂悤�Ƃ������_�����̎����ɂȂ����Ă���B
�ቹ���́AWE555�����V�X�e���Ŏg�p����RCA MI-1444�t�B�[���h�^38�Z���`�E�E�[�t�@�[���Q���A��ʂ��J�������Ɏ��t���������̂��̂ŁA�ቹ��(����f�[�^�̂悤��)��荞�݂̂��߂ɂ���قǏo�Ȃ��B(���͂��Ȃ葬���B)���̏�ԂŃV�X�e���̎��g����������������B����́A20Hz����20KHz�܂ł̃T�C���g��A���X�B�[�v�����A������}�C�N�ō̉����AFFT�������s�[�N�E���x����A���v���b�g�����B�W�F�l�[���[�^�Ƒ������u�n�̎��g�������́A�قڃt���b�g�ŁA�X�s�[�J�[�̎������ɂ͂قƂ�lje�����Ȃ��͂����B����Ɏg�p�̃}�C�N���z���́A������(���̓W�����N�Ƃ��Ă�����200�~�H�Ŕ������I�[�f�B�I�p�̑�^�̕������APC�p�̃I���`���̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B)�_�C�i�~�b�N�^�Ȃ̂ŁA���g�������f�[�^�������o�Ă���͂���������͎��g�������̕�̎����Ȃ̂ō�������������悢���낤�ƁA�������������m�Ŏ������Ă݂�B�Ȃɂ��g���C���Ă݂邱�ƂɈӋ`������B�f�[�^���͂����肵�Ă���A���ƂŃ}�C�N�̓������Ƃ��ĕ��������B����ʒu�̓z�[���J�������ʂ���Q���[�g���ŁA�T�X�S�`�ƂP�S�S�S�̃N���X�I�[�o�[�́A�Q�Q�O�g�� 6dB/Oct�ł���B���}�O���t�̃��x���\���͉����̕\���ł͂Ȃ��A��荞���C���̃��x�����\�t�g�E�F�A�ŏ��������\���ɂȂ��Ă���̂ŁA���ΓI�Ɍ��Ă������������B
���̎ʐ^�̐^���̑��u���ASH-D1000�Ƃ���DSP(�e�N�j�N�X�ł́APAP�ƌĂ�ł���)�ŁA�f�B�W�^���ő��@�\�ȐM���������ł�����̂��B����́A�f�B�W�^���łQ�P�`�����l���̃C�R���C�W���O�������Ē������Ă݂�B
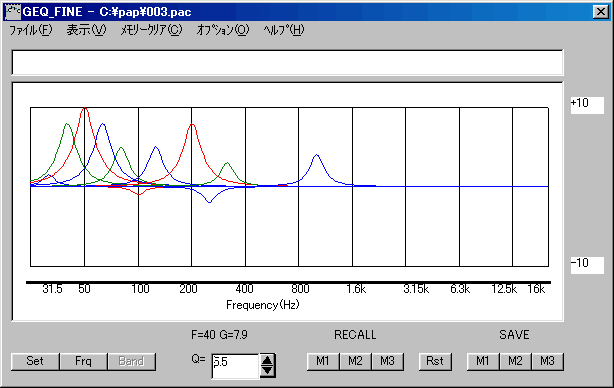
���̃O���t�B�b�N�X�̏�̂ق����A�C���O�̃V�X�e���̎��g����������ŁA���̂ق����C����̓����ł���B�����̗�����g�p���邱�Ƃɂ��A���ʂ𓊓����Ȃ���Ή����ł��Ȃ��������̎��g���������ɂ������̈�r�����邱�Ƃ��킩��B
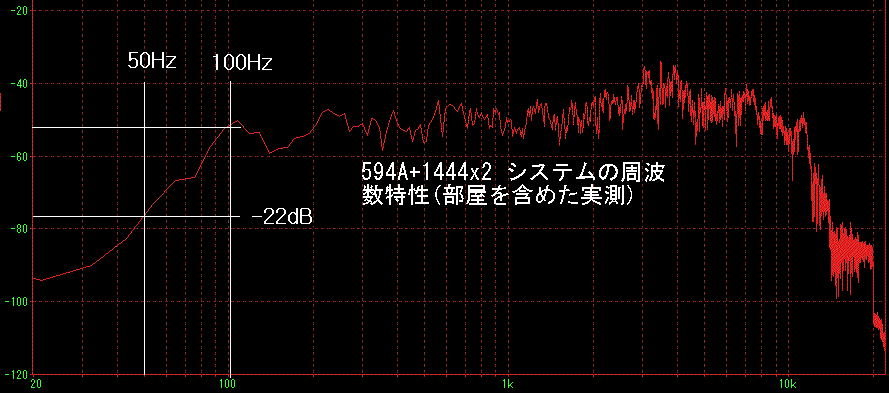
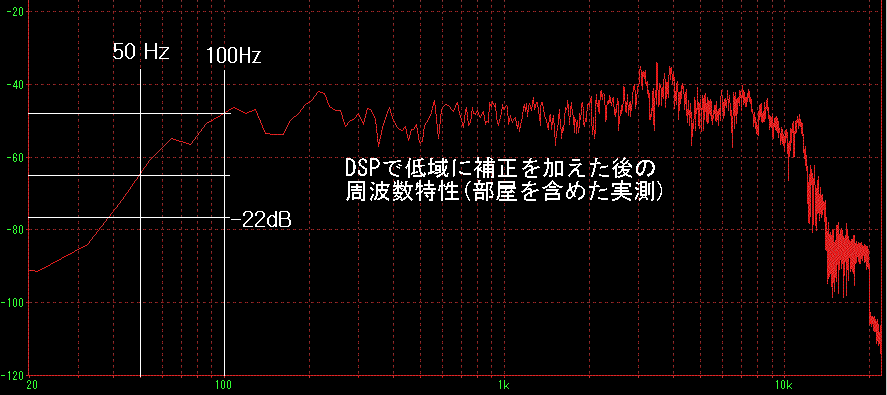
SH-D1000(�l�i��10���~)�̓���DA�R���o�[�^���烁�����E�A���v�Ɍq�����̂ŁA�����́������I�Ƃ������x���ł͂��������A���̂Ԃ�����Ă��Ē����Ă݂Ă��ACD�̍Đ��ʼn��̃o�����X���i�i�Ɍ��サ���B���S�����̂͂��̕�ɂ��A���R�[�f�B���O�Z�t�̉�����̈Ӑ}�����Ăɂ킩�邱�Ƃł���B�^���X�^�W�I�ł́A�Ȃ�قǗ��z�ɋ߂���ԂŃ��j�^�����Ă��邾�낤����A���̃��j�^���Ȃ���~�L�V���O���ĉ����������킯�ł���B�Đ����̎��g�����������̏�Ԃɋ߂��Ȃ�Ȃ�قlj�����̈Ӑ}���Č����₷���Ȃ�͓̂����ł���B�����A�Ȃ���̂킩��Ȃ�����CD���A���̕�Ő����Ȃ����Ă݂����Ǝv�����B�Ђ���Ƃ���Ɖ�X�́A�����ꂽ�^����F�ዾ�������Ē����Ă����̂����m��Ȃ��B
�������\��AD�R���o�[�^��DA�R���o�[�^��v���ĐM�������͊Ԃɋ���DSP�ɍ�Ƃ�����B���C���A���v�̓X�s�[�J�[�ɍ��킹�Ēǂ�����ł��܂��B�M�������͑S�f�B�W�^���H���ł̓A�i���O�I�����̗��Ȃ�(�͂���)�B���y�\�[�X���܂邲�ƃf�B�W�^���ŋ��僁�����[�ɓ���Ă����A�����x�̃N���b�N�����Ŏ��o��DA�ϊ�����B�A�i���O�������w�I�ɂ͕��ʂ��ŏI�I�ɂ��̂��������E�����A�f�B�W�^������͂蕨�ʂł���B�������ăn�C�G���h�̃V�X�e���́A�G���K���g�ȉ���Nj����邽�߂ɃG���t�@���g�ɂȂ��Ă����B